 1996年2月10日土曜日朝8時頃、豊浜トンネル(国道229号線 古平−余市の中間地点)の上部岩石が大崩落しトンネルの入口から40mにわたって巻出天井部分を押しつぶした。
1996年2月10日土曜日朝8時頃、豊浜トンネル(国道229号線 古平−余市の中間地点)の上部岩石が大崩落しトンネルの入口から40mにわたって巻出天井部分を押しつぶした。
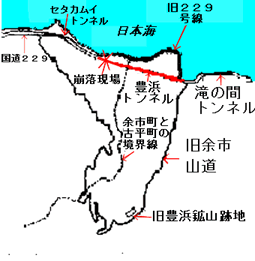 古平21では「危険なイメージが広がった豊浜トンネルは別ルートの検討が必要だ」と言うことで、平成8年6月23日 に17人で、1963年に開通する以前に使われていた旧余市山道を歩いてみました。
古平21では「危険なイメージが広がった豊浜トンネルは別ルートの検討が必要だ」と言うことで、平成8年6月23日 に17人で、1963年に開通する以前に使われていた旧余市山道を歩いてみました。 約2時間半で旧豊浜鉱山跡に出ました。
約2時間半で旧豊浜鉱山跡に出ました。
平成8年6月25日 新聞報道で、豊浜トンネル「代替道」道がルート探しにとりかかる。
という記事が掲載されました。
さっそく、道庁目安箱(道庁が、ニフティやPC−VANから道民の声を電子メールで受け付ける)に掲載記事について詳しい内容を聞いたところ、7月3日に返答をもらいました。
−−前略−−「余市町、古平町、積丹町の内陸部には、道道、町道、農道、林道など車の通行が可能な道路の他に、登山道や昭和30年代までに使われていた旧国道、古い時代のものと考えられる踏み分け道などがあります。 しかし、現在ほとんど使われていないこれらの道の現況は不明な部分が多いことからこのたび、緊急にこれらの全体的な把握をするため、資料作成の調査を行うこととしたものです。
今後は、この調査結果を踏まえ、通行の可否、通行を可能にする方策など、車が通行できる可能性について早期に検討したいと考えているところです。」−−後略−−
この様な内容でした。
私にとって、たいへん希望の持てる内容でした、是非この別ルートが、実現化されるよう、皆で力を合わせ、がんばりたいと思います。
事故より半年がたった、平成8年8月10日現在の状況を報告します。
現場付近の不安定な岩を8月中に落とし、9月より事故のあったトンネルを応急工事(鉄骨・発泡スチロールを使った工法)をして、年内の開通を目指しています(仮復旧)。
本復旧は、現在の仮復旧トンネルの安全性・現在のルート・迂回路ルート等を検討し年内に結論を出すことにしている様です。
この夏・秋ごろ開通予定されていた、積丹半島未通区間も
危険箇所が数箇所あり、今だ開通のめどが立っておらず来年になる可能性もある様です。
11月1日開通しました
夏の積丹観光も昨年と比べ、交通量で約40%減少となっています、いち早い復旧と安全宣言が求められている状況です。
9月14日、トンネル崩落事故の原因を解明する目的で、開発局が設置した事故調査委は、最終(6回目)の見解を開発局に提出した。
結論は、今回の事故の原因でもある亀裂の確認・崩落の予知は学術的にも不可能であった、又トンネルの掘削が崩落につながる可能性は極めて小さかったとして、開発局の責任には言及しないままの最終報告であった。
開発局側は、事故調査委の報告書を検討し、できるだけ早く局側の考え方を示す、とコメントした。
今後開発局は、遺族補償・本格復旧ルート選定・慰霊碑建立・報告書の、事故再発を防ぐための提言の実践 等の課題に移りたい考えである。
しかし、一部新聞等によると、文案作成は局主導で行われたとの報道もあり、開発局による調査委設置のプロセスに問題があったのではないかとの疑問の声もある。
北海道警察は、独自に刑事責任の追及で捜査を進めているが刑事責任の追及までは、かなり時間を要するようだ。
上記 新聞報道を参考に記載
某業界新聞の記事によると、開発局が新トンネルの掘削を来年中より始め、4年後開通見通しの方針を固めたと報じられました。
新トンネルは、事故トンネルの余市側(崩落現場の反対側)数百メートルをそのまま使い、そこより山側に向かって堀り、旧道を歩く で掲載した地図のセタカムイトンネルを通らずに古平側に抜け、国道229号線につながる予定です。
これが最終のルート決定なのかは、解りませんが情報として掲載しました。

10月13日現在の豊浜トンネルです
信号による片側交通規制が続けられ、年内
の仮復旧(事故トンネルを修復し、事故前
の状況に戻す)に向けて工事が進められています。

トンネル左側面
左側から見たトンネル工事の様子です。
奥の鉄骨の部分が、崩落により潰された所です。
開発局の発表によると、年内復旧を目指していた豊浜ンネルが 12月11日に開通するそうです。
崩落事故遺族会(210の会)は12月10日に事故現場最後の法要を行います。
12月11日に仮復旧の形で車両が通行することが可能になり、そのため事故現場での法要が今後出来ないので、来年2月10日の事故1周忌法要を繰上げて行うそうです。
私自身も毎日この豊浜トンネルを利用するので、事故現場の上を走ることになります、ご遺族の方々にしてみれば、さぞ辛いことだと思います。
 12月11日 午前6時30分、豊浜トンネルが仮復旧という形で通行が可能になりました。
12月11日 午前6時30分、豊浜トンネルが仮復旧という形で通行が可能になりました。
12月17日開発局が本格復旧ルート決定し発表しました、決定ルートは”トンネル新ルート”で掲載したルートに近いものでした。
現在仮復旧した、豊浜トンネルの途中から山側に新トンネルを堀り、セタカムイ(古平方面へ向かって豊浜トンネルの次にあるトンネル)トンネルの途中に抜ける1.2Kmのルートです。
遺族側の要望が強かったルートで、4年後の完成予定を目指すそうです。
私の個人的な意見ですが、このルートの他にもう1本、代替道となる道路が必要だと思っています、11月28日に道庁目安箱で頂いた回答では、まだ検討中との事でした。
長期的な計画になるかも知れませんが、是非 代替ルートを実現化してほしいものです。
12月29日北海道警察の委嘱で、専門家が調査していた鑑定結果が捜査本部に提出されました。
提出内容は公表はされませんでしたが、北海道警察では、専門家鑑定結果・開発局の提出書類・地域住民の聞取り等を総合して、開発局の過失責任の有無を問えるのかどうかを判断する様です。
しかし、最終的な結論が出るのは、まだかなり先になるようです。
この事故で旦那さんを亡くされた奥さんが、今日当店へ買い物にいらしゃいました、「今年は1人分だからねぇ・・・」と寂しそうに言われた言葉が耳に残ります。
平成9年2月7日 北海道警察は、崩落前、事故現場付近に度々落石が起こっていたのに、開発局が適切に措置していなかったとみて刑事責任を問う方針を固めました。
平成8年2月10日に起こった豊浜トンネル崩落事故から1年が経ちました、犠牲になられたご家庭では1周忌の法要が営まれています。
報道関係の車が、古平町のあちこちに見受けられました、報道の車を見ると1年前を思い出してしまいます。
現在、仮復旧という形でトンネルは何事も無かったように交互通行が可能になり、私達町民の生活も事故前と変わらない日々になりました。
この事故は、いったい誰に責任があるのでしょう?
そして、この道路を生活の為に使用している私達は、これから何をすればいいのでしょう?
1年という節目を迎え、今 もう一度考えようと思っています。
平成9年8月25日午後2時頃、豊浜トンネル事故と同じ229号線、約170k離れた島牧村第2白糸トンネルで岩盤崩落が発生しました。
8/26日午後9時現在、車両等が巻込まれたと言う発表はありませんが、トンネルの巻だし部分を押し潰した映像は、豊浜トンネル事故と同じ様に映りました、崩落した土砂は豊浜の約2倍の量との報道です。
このトンネルは、豊浜トンネル事故後行われた緊急点検で最も高い危険な箇所として、落石防止の金網と巻だし部分の衝撃暖和用の発泡スチロールを設置していたとの事です、しかし今回の崩落にはまったく効果がありませんでした。
今回の崩落は豊浜トンネルと同じように、まったく予想の出来ない事だったのでしょうか?
事故後の管理者の対応はどうだったでしょう?
豊浜の教訓は・・・?
あれだけ指摘された危機管理能力は・・・?
この道路は、日中1時間10数台程度の僅かな交通量です、しかし住民には病院や買物に利用する貴重な道路、まして国道なのです。
たいへんな復旧に関る作業をしている方々に2次災害が起きぬよう、万全を期しながらも早急な復旧を切に希望します。
 平成9年8月27日の豊浜トンネルです
平成9年8月27日の豊浜トンネルです
トンネル上部の発泡スチロールの上に土が盛られ、奇麗に芝がはられています。
まるで何も無かった様に・・。
第2白糸トンネルでは、未だに車両等が巻込まれたかどうかの確認が出来ていません、TVニュースで、開発局は豊浜トンネル事故の時と同じ様に予測出来なかったと言ってました、どのような状態なら予測出来るのでしょう?
予算等の問題があるなら、国は危険箇所の対策費を別会計として是非、予算化して欲しいものです。
開発局は、第2白糸トンネル崩落土砂の撤去をあきらめ(人の被害はなかったと判断)、99年4月までに新ルート(山側掘削)でのトンネル着工を発表しました。
付近住民の皆様は、まだまだ不便が続く様ですが、是非 安全な道路を完成してほしいと思います。
98年2月10日豊浜トンネル崩落事故から2年が経ちました。
新ルートである豊浜新トンネルは、2001年秋完成を目指し工事が進められています。
建設グラフ記事
それと同時に 危険個所防災工事の為、余市−古平間は、98年3月24日まで午後10時から翌朝5時まで通行止めになっています。
町民にとって事故から2年という時が経過しても、この工事作業を見ながらの通行は、忘れたくとも、忘れられないのが本音です。
この事故を受け、北海道内の危険個所調査では、国道142ヶ所が対策を要すると確認されました、すべての対策工事を完了させるのにまだ約5年の月日が掛かるそうです。
是非 1日でも早く対処をしてほしいものです。
そして、二度とこの様な事故が起こらぬ様、確実な崩落の予測技術の確立が実現出来ます事を切に希望します。
遺族の方々、観光に携る方々、常にこの道路を生活の道として利用する方々、
さまざまな意見があります、しかし、共通する意見は一つ安全な道です。
1998年6月23日、余市警察署は、開発局元幹部2名を札幌地検に書類送検しました。
1991年12月初旬に事故現場付近で約300tの落石があったのに放置した、もしこの時点で周辺調査、及び危険防止策をとればこの事故は起きなかったとの疑いです。
ただ、札幌地検が起訴まで持込めるかは未定で、起訴までにはまだ難しい判断が多いとの事です。
91年の崩落個所は、大崩落したすぐ隣の部分で、豊浜トンネルの旧道側(海側)に落ちました、私も落ちていた岩盤は見ています、確かにこの時点で、道路管理者が大事と捉えれば何らかの対処は出来たのではと考えられます、いずれにせよ20名の命を奪ったこの事故、ご遺族の訴訟もまだ続いています、そして、付近の道路も安全対策の工事が現在もなお続けられています建設グラフ記事、私たちにとって、まだまだ鮮明な記憶として残り、忘れられない状況が続いています。

