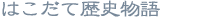







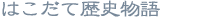 |
       |
| ■戦時下の函館 | 【はこだて歴史物語】 |
|
【函館空襲】 1945年(昭和20)7月14・15日、北海道地方の空襲により、函館市も大きな被害を受け、多くの死傷者が出ました。 特に青函連絡船の殆どが沈没・炎上するという大打撃を受けました。 【使えなかった(?)…函館要塞】 函館要塞は日清戦争後の1898年(明治31)、4年の歳月をかけて函館山造られた、天然の地形を利用した軍事要塞です。 大小合わせて5ヵ所の砲台、77の施設が築かれ、第2次世界大戦の終結まで軍事機密厳守のため、立ち入りや写真撮影、測量のほか、写生までもが禁止されました。 しかし、実際に榴弾砲が火を噴くことはなく、要塞がある函館には攻めてこないだろうと信じていた市民も、堂々と市内に進入してくる敵機を見て、不思議に思ったそうです。 後にこの要塞の設備は、近代戦にはとても通用するものではなかったことが分かりました。 |
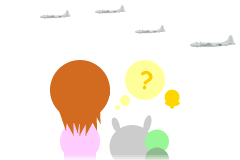 【参考】 御殿山第二砲台跡 |
 | |
| ■北洋漁業の終焉 | 【はこだて歴史物語】 |
|
漁業基地を持つ函館にとってサケ・マス漁を主とした北洋漁業は、明治以降の地元経済を支えてきた一大産業でしたが、戦後、占領軍によって日本の漁場が制限され、北洋漁業の喪失という事態に至りました。
1952年(昭和27)に再開され、函館港は再び活気を取り戻しますが、その後、ソビエトとの幾度の交渉の末、日本の漁業水域が次第に縮小され、母船会社も撤退しました。 1989年(平成元)、函館港から出漁した独航船が最後となりました。 |
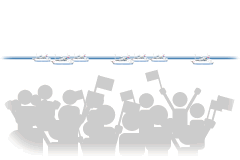 【参考】 函館市北洋資料館 |
 | |
| ■さようなら 青函連絡船 | 【はこだて歴史物語】 |
|
青函連絡船が就航したのは1908年(明治41)のことです。 その後の交通事情の変化により、80年後の1988年(昭和63)3月13日、青函トンネルの開業に伴い、その歴史に幕を降ろしました。 ちなみに、青函連絡船の総運行距離は80,894,813㎞…これは地球を2,019周もする距離に相当します。 【青函トンネル】 1964年(昭和39)着工し、24年後に営業を開始しました。 総延長53.85㎞の世界最長の海底トンネル開通により、青函連絡船で約4時間を要した青森-函館間は約2時間…さらには新幹線の開業時には約40分へと短縮される予定となっています。 |
 青函連絡船記念館摩周丸 |
 | |
| ■函館市電の歴史 | 【はこだて歴史物語】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【箱館ハイカラ號】 1910年(明治10)頃に製造された車両を購入、1918年(大正7)より運行開始…1937年(昭和12)改造後、ササラ式除雪車として運行。 1993年(平成5)「復元チンチン電車・箱館ハイカラ號」の愛称で当時の姿に復元、再び函館の街を走っています。 ちなみに「ちんちん電車」とは、車掌が運転士との連絡合図に使う信鈴装置のひもを引くとチンチンと鳴ることが名前の由来です。 |
 1950年(昭和25)製造された車両"530号"  箱館ハイカラ號 【参考】 市電路線図 |
||||||||||||||||||||||||||||||